こんにちは! ノアの杜 長屋です。
ご火葬の際に様々な副葬品を一緒に火葬してほしいという
ご要望は多くございます。
そしてノアの杜といたしましてもなるべくご家族様の
ご意向に沿えられるように努めさせていただいております。

しかしながらお骨をより綺麗に残す為には
沢山の副葬品はお勧めできない場合があります。
人間と比べるとペットさんのお骨は細くて小さく、
またご遺体によっては崩れやすい為、
不適切な副葬品をいれてしまうと公害問題だけでなく、
ご拾骨の際に綺麗にお骨を拾う事が出来ません。
それではどんな副葬品なら大丈夫なのか・・・?!
〇【納められる副葬品】
・お花
・ご飯やおやつ類
・お手紙お写真(少量)
・「おむつ」生地の薄いお洋服
※ タオル類は薄手の物に限り、お断りする場合があります。
△【素材による】
・おもちゃ
・首輪
・厚手のタオル類
×【納められない物】
・化学繊維類
・金属、ガラス類
・お布団やベッド、棺(どのような素材であっても)
※ご火葬にあたり、以下の物は燃焼の妨げになります。
・石油化学製品(ビニール、プラスチック、化学繊維、ボール等)
・燃えずらい物(大量の食べ物、水分量の多い果実類やお水、カーボン繊維等)
・燃えない物(ガラス、金属類は溶けてお骨に付着してしまいます)
上記のようなご火葬が困難な物を入れてしまうと
異常燃焼を起こす場合があります。
異常燃焼とは、燃焼物の温度上昇に伴い熱分解量が増した
未燃焼ガスと酸素濃度のバランスが崩れた時に起こり、
炭化したガスが煙突から排出されます。
そうすると煙とにおいの処理が困難になってしまいます。
しかしそれは素材などにもよりけりで、
例えば100%パルプとサテン生地で作られたお布団などであれば
燃焼効率もよく灰がほとんど残りません。
このように、副葬品でも大丈夫な物、そうでない物、
素材によっては大丈夫な物など様々です。
ノアの杜では少しでもご家族様のご意向に沿えられるように
努めさせていただいておりますので、
ご希望の副葬品についてや、その他ご不明な点などがございましたら
いつでもお尋ねくださいね。
ノアの杜 長屋
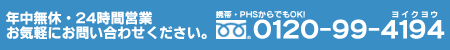
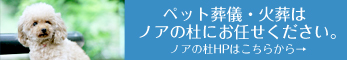

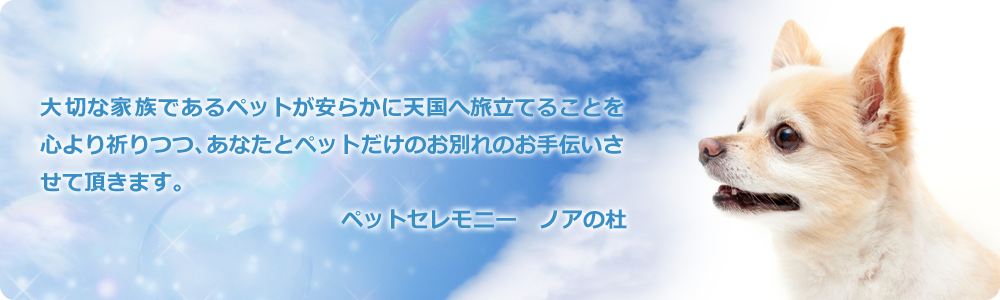



 先日とある方から「引取でのご火葬」(引取はご火葬に立ち会いはなく、お骨のご確認、ご返骨は無くお骨はお寺への永代供養)のご依頼を頂きました。 岐阜から一時間半近くの県内の山の中にお住いの方です。 「野良の子、自宅の庭で亡くなってて」とのことでした。 亡くなった野良の子の引取からご火葬は行政が行うことが殆どですがご自宅の敷地の中では対応して頂けません。 この方もやはり「土に埋めてやろうか」と悩まれたそうです。 当社へのご依頼はやはり費用がかかってきます。そんな中で当社にご依頼を頂きました。 お伺いし「越したばかりで山の中は日が沈むのが早くてやっぱり寒い~」とニコニコしながらお話しされてました。 そこでこんなことをお話しされたことがとても印象的でした。 『猫ちゃんは何処かへ姿を消して最後を迎えることが多いって聞くけど、表現が違うかもだけど、最後の場所をここに選んでくれてなんだか光栄に思えて』と、合掌されてました。 きっと、猫ちゃんがご主人様を遠くから見て選んだんだろうな、手厚く送ってくれることを知っていたんだと思います。 飼い猫ではなかったのですが亡くなってからですがこのご縁、きっと飼い主様を天国から見守ってくれるとと思います。
猫ちゃんとは来世できっと良いご縁が結ばれると思います。 また、これから起こり得る飼い主様に降りかかる「疫」からもずっと守ってくれると思います。 実際に自己負担で費用をかけてなかなか出来ることではありません。 頭の下がる思いで出発させて頂きました。 後は当社にお任せくださいね。 当社にて責任もってご火葬からお寺への永代供養までさせて頂きます。 ペットセレモニーノアの杜 後藤
先日とある方から「引取でのご火葬」(引取はご火葬に立ち会いはなく、お骨のご確認、ご返骨は無くお骨はお寺への永代供養)のご依頼を頂きました。 岐阜から一時間半近くの県内の山の中にお住いの方です。 「野良の子、自宅の庭で亡くなってて」とのことでした。 亡くなった野良の子の引取からご火葬は行政が行うことが殆どですがご自宅の敷地の中では対応して頂けません。 この方もやはり「土に埋めてやろうか」と悩まれたそうです。 当社へのご依頼はやはり費用がかかってきます。そんな中で当社にご依頼を頂きました。 お伺いし「越したばかりで山の中は日が沈むのが早くてやっぱり寒い~」とニコニコしながらお話しされてました。 そこでこんなことをお話しされたことがとても印象的でした。 『猫ちゃんは何処かへ姿を消して最後を迎えることが多いって聞くけど、表現が違うかもだけど、最後の場所をここに選んでくれてなんだか光栄に思えて』と、合掌されてました。 きっと、猫ちゃんがご主人様を遠くから見て選んだんだろうな、手厚く送ってくれることを知っていたんだと思います。 飼い猫ではなかったのですが亡くなってからですがこのご縁、きっと飼い主様を天国から見守ってくれるとと思います。
猫ちゃんとは来世できっと良いご縁が結ばれると思います。 また、これから起こり得る飼い主様に降りかかる「疫」からもずっと守ってくれると思います。 実際に自己負担で費用をかけてなかなか出来ることではありません。 頭の下がる思いで出発させて頂きました。 後は当社にお任せくださいね。 当社にて責任もってご火葬からお寺への永代供養までさせて頂きます。 ペットセレモニーノアの杜 後藤

 大切なペットさんの命、守ってあげて下さいね。 ペットセレモニーノアの杜 後藤
大切なペットさんの命、守ってあげて下さいね。 ペットセレモニーノアの杜 後藤




